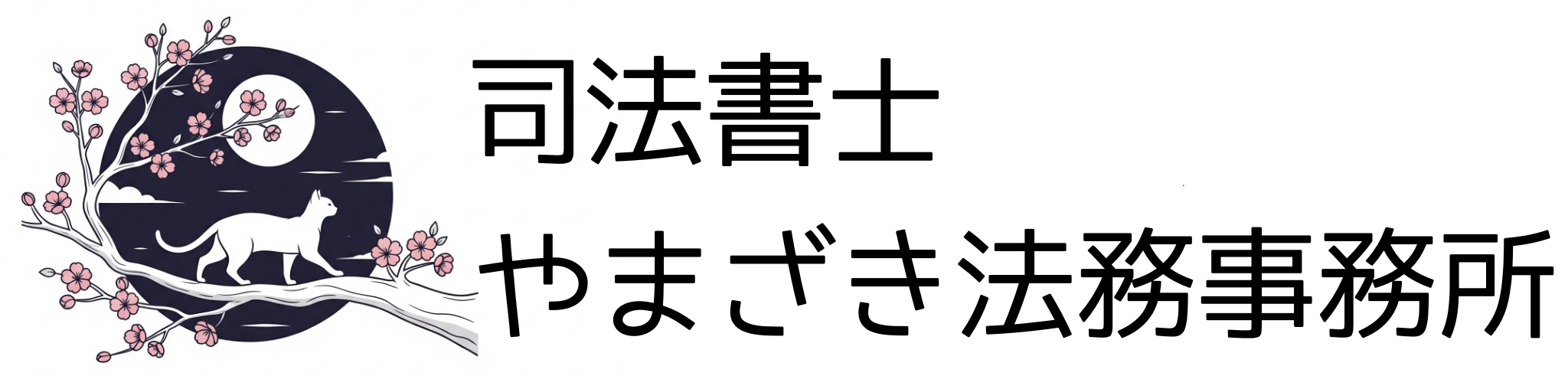🏠 相続登記が義務化されました!—「実家」や「土地」を相続したら、今すぐ確認を!
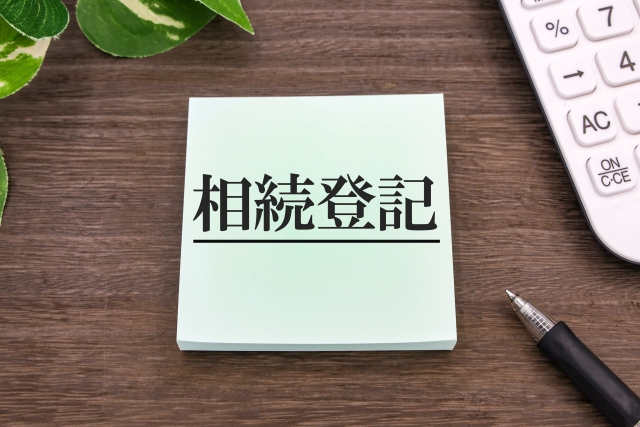
🚨 2024年4月1日からスタート! あなたの相続手続きは大丈夫ですか?
2024年(令和6年)4月1日から、不動産(土地や建物)を相続した際の手続きが大きく変わりました。それは、「相続登記の義務化」です。
これは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産について、相続人の方がご自身の名義に変更する「相続登記」が、法律上の義務になったということです。
📌 義務化のポイントを分かりやすく解説!
| 項目 | 内容 |
| いつから? | 2024年(令和6年)4月1日 からスタート |
| 誰が対象? | 相続や遺言(遺贈)で不動産を取得したすべての方 |
| いつまでに? | 不動産を取得したことを知った日、または2024年4月1日のいずれか遅い日から3年以内 |
⚠️ 東三河特有の注意点!「先祖代々の土地」を守るために
相続登記の義務化は全国共通のルールですが、私たちの暮らす東三河地域においては、特に重要な意味を持ちます。
🌾 なぜ東三河で相続登記が大切なのか?
東三河地域は、都市部への人口流出、高齢化・過疎化が進んでいる地域が多く、以下のような問題が深刻化しています。
- 「所有者不明の土地」が多い:相続登記が長年放置され、何代にもわたる「共有状態」になっている農地や山林、空き家が少なくありません。義務化は、こうした状態を解消し、所有権を明確にするためのものです。
- 「実家・空き家問題」が深刻化:都市部に住んでいる相続人が、地元に残した実家や土地をそのまま放置しているケースが増えています。登記をせずにいると、将来的に売却や賃貸をしようとしても、手続きが極めて煩雑になり、活用が難しくなります。
- 子や孫への大きな負担:手続きを放置すれば、相続人がさらに増え、次の世代が手続きをしようとしたときには、数十人もの相続人全員の実印と同意が必要になる、といった膨大な手間と費用がかかってしまいます。
「ご先祖様から受け継いだ大切な土地」を守り、将来的な活用をスムーズにするためにも、この機会に必ず相続登記を済ませましょう。
📅 特に注意!「昔の相続」も義務の対象です
「親や祖父母が亡くなったのがずいぶん前だけど…」という方も要注意です。
この義務化は、2024年4月1日よりも前に発生した相続についても適用されます。
- 昔の相続のスタート日: 原則として、2024年4月1日
- 申請期限: 2024年4月1日から3年以内(つまり、2027年3月31日まで)
期限が迫っていますので、まだ名義変更が済んでいない不動産がある場合は、今すぐ確認が必要です。
⚠️ 義務を怠るとどうなる? 最大10万円の「ペナルティ(過料)」
正当な理由がないにもかかわらず、この相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の「過料(かりょう)」というペナルティが科される可能性があります。手続きを先延ばしにせず、期限内に完了させることが重要です。
⚖️ 東三河の相続に強い当司法書士事務所にお任せください!
相続登記の手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集めたり、遺産分割協議書を作成したりと、一般の方には馴染みのない複雑な作業が必要です。
東三河の地域事情を熟知した当事務所であれば、「共有者が多数に上る農地・山林」といった、地域特有の複雑な相続案件についても、迅速かつ的確に対応いたします。
✅ 当事務所にご依頼いただくメリット
- 複雑なケースにも対応: 数代前の相続まで遡る必要がある「数次相続」や、相続人の数が多く難航しがちなケースも、豊富な経験で解決に導きます。
- 必要な書類の収集をすべて代行: 複雑な戸籍謄本の収集や、登記に必要なすべての書類を迅速に準備します。
- 手間と時間の削減: お客様は面倒な手続きから解放され、ご自身の時間や精神的な負担を軽減できます。
- 地元の専門家ネットワーク: 相続税(税理士)や未登記建物の手続き(土地家屋調査士)など、東三河で活動する他の専門家とも連携し、お客様の相続問題を総合的にサポートします。
相続登記の義務化により、手続きの必要性が高まっています。「どこから手を付けていいかわからない」「もう期限が迫っている」という方は、まずは一度、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
【お問合せ・ご予約はこちら】
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください